クラブ長は今
生徒のみなさんの作業の参考になるように、少し先行するような感じでアップしていきます。
[1週目] 紙粘土+エポキパテでの本体制作
テントウムシとカエルの仮組、脚、後翅の制作工程です。
今回の”ピカピカ”というキーワードから、どこかの部位が光る虫を考えたのですが、結局思いついたのは、言葉から連想した”点灯虫(テントウムシ)”。
見た目がかわいい赤地に黒い水玉模様のナナホシテントウをモチーフにし、前翅を開閉できるようにして、内部を光らせようと計画しています。
そして前回(2014年 vol.2)とつながりを持たせたかったので、テーマだったカエルも一緒に制作。
これからの1ヶ月間、完成目指して進めていきます!
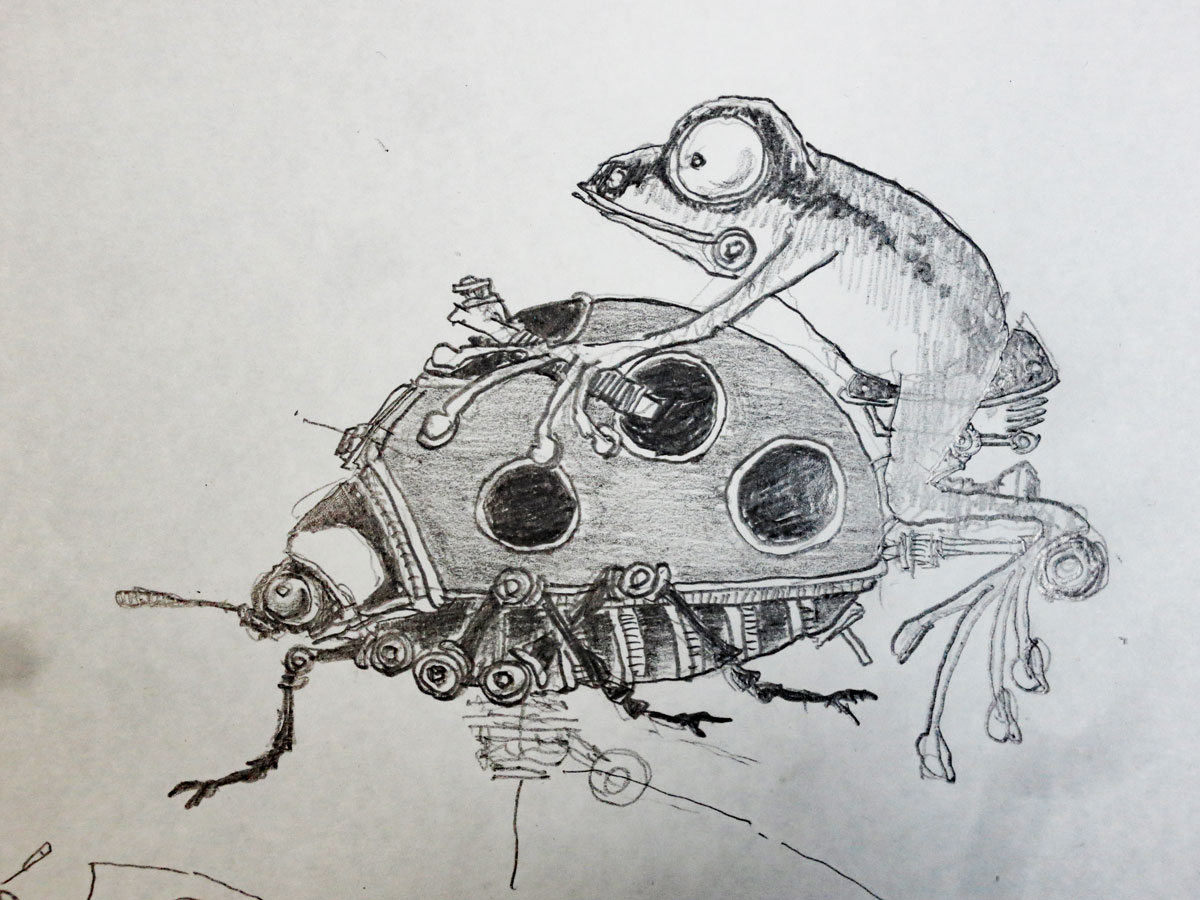
UCC3_1.01
ラフ案。イメージは、テントウムシ型のホバーバイク。
操縦するライダーは、アマガエルです。
浮いたような展示になる土台ベースを考えています。
テントウムシの鞘翅が開閉し、後翅が中からひろがるようにしたいのですが、
内部スペースの状況次第では、付け替え式かなあ・・・
ヘッドライトと内部エンジンをLEDを使って光るように加工します。

UCC3_1.02
まずは、紙粘土でテントウムシの本体制作から。
お椀を伏せたような形をしている頭部、胸部、上翅のおおまかな形状をつくります。
目には、アクリル球φ10mmを埋め込んでます。
ここをヘッドライトのように光らせる予定です。
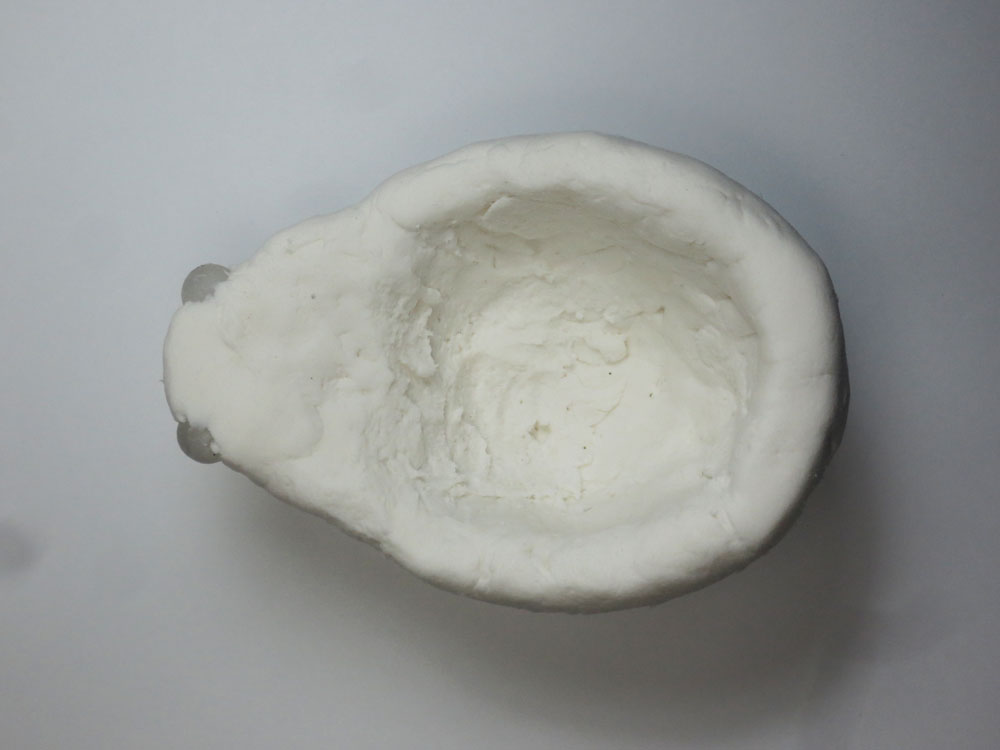
UCC3_1.03
テントウムシの内部は、光るエンジンやLED電源の為に、乾電池BOXを設置するので、
中空にします。
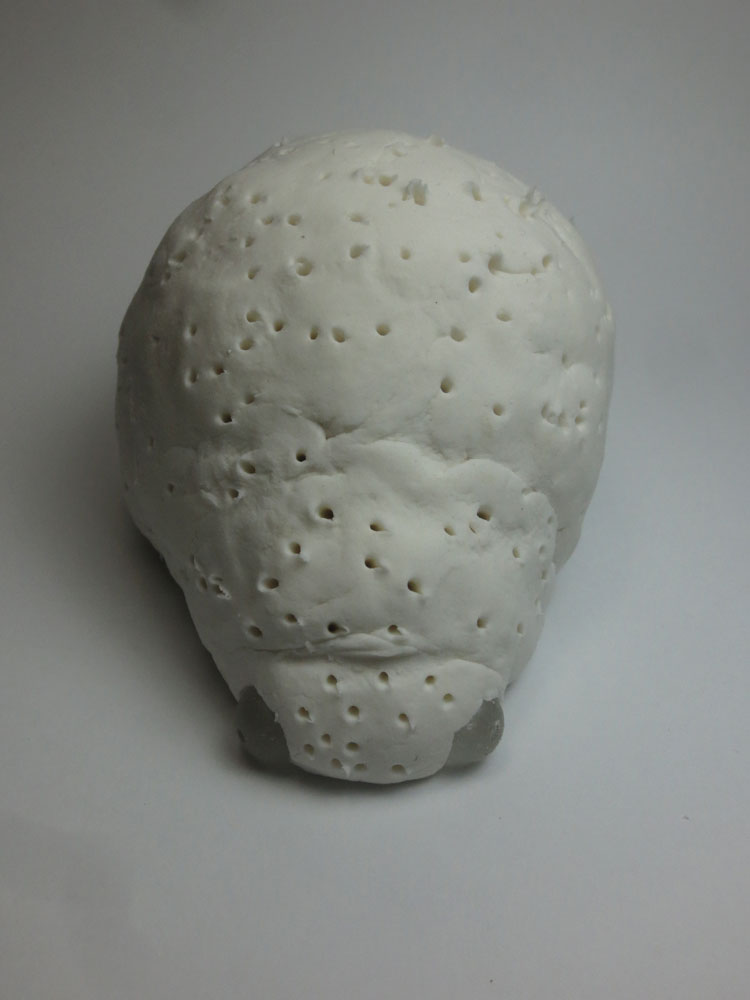
UCC3_1.04
紙粘土の肉厚がある場合、乾燥を促進させるのと、
次に紙粘土を足すときに食いつきが良くなるように
千枚通しのような先端が尖ったもので、穴をたくさんあけておきます。
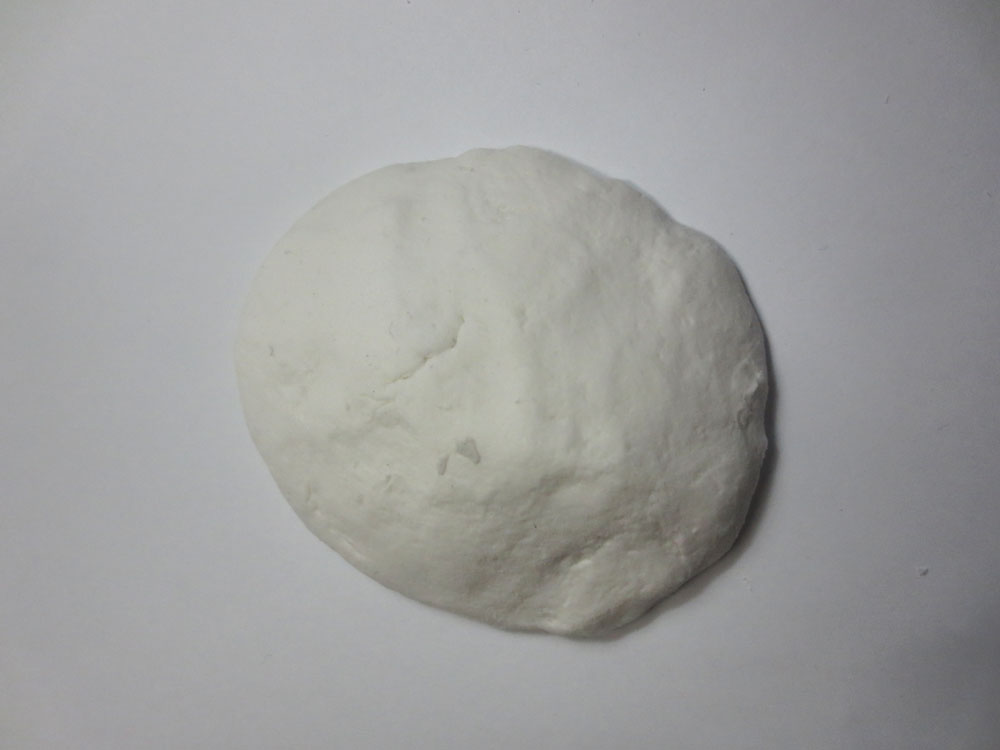
UCC3_1.05
大きさを合わせて、腹側も紙粘土で制作。

UCC3_1.06
上記で制作した腹側の紙粘土を背側本体と合わせ、この状態で、一度完全に乾燥させます。

UCC3_1.07
紙粘土が乾燥した状態。
これから成形していくために、鉛筆で基準になる線を書いて作業していきます。

UCC3_1.08
横から見たところ。
紙粘土は乾燥すると歪むので、それを補正していきます。
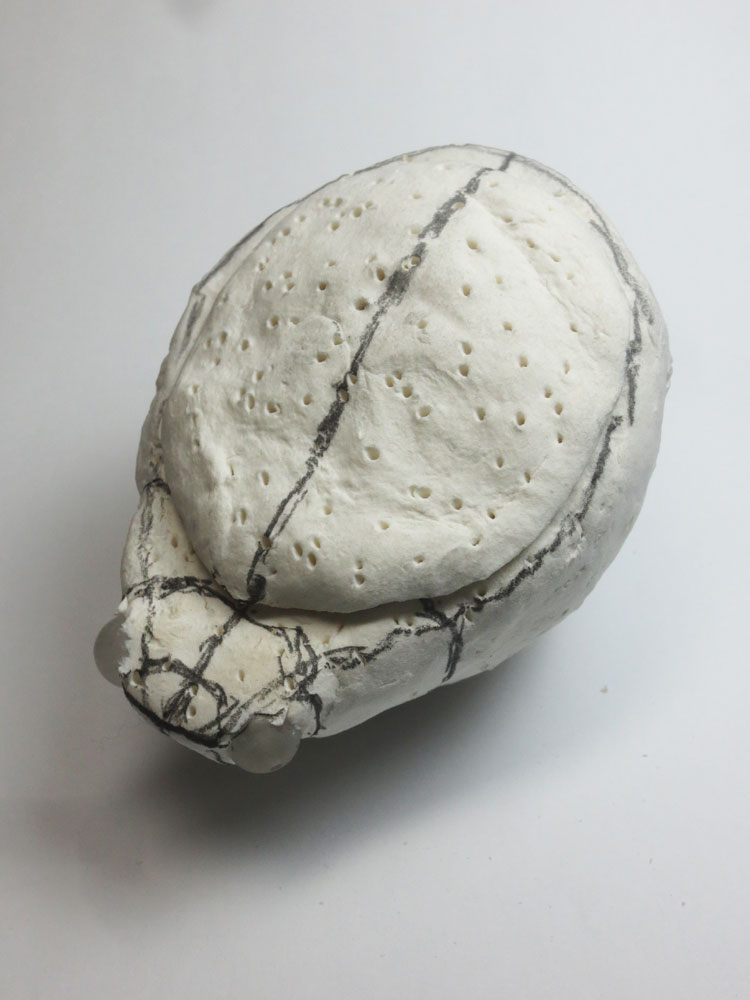
UCC3_1.09
腹側。
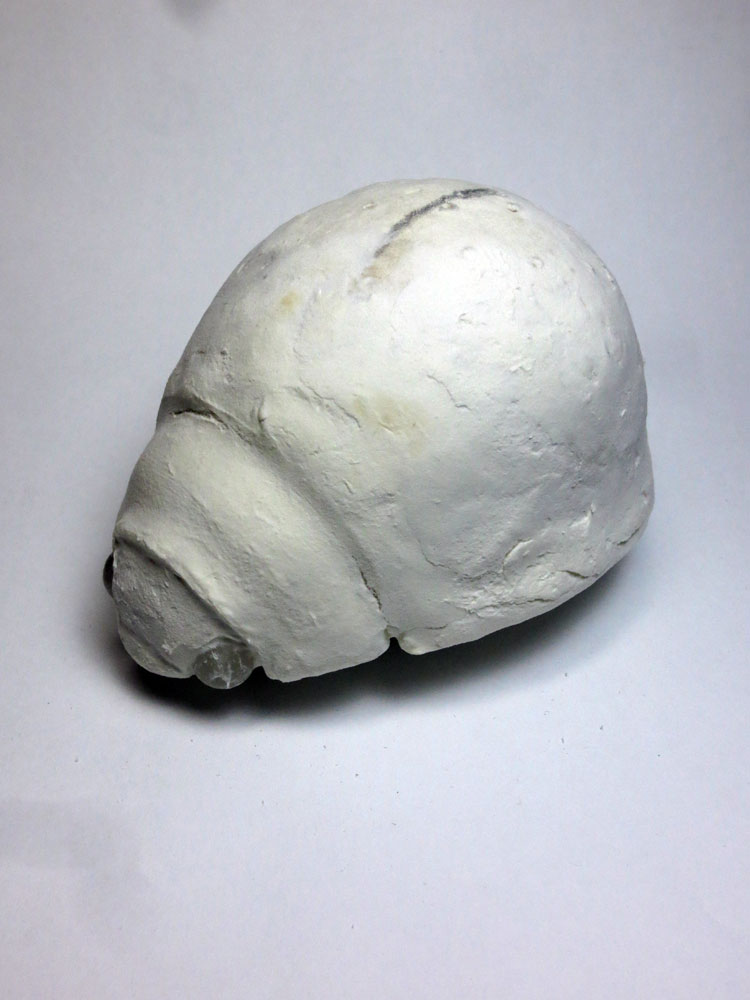
UCC3_1.10
中心線を基準に左右対称になるよう、形を成形していくのですが、
1度で完成させるのではく、ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し作業を
何回も繰り返すようにして、求める形に近づけていきます。

UCC3_1.11
この画像で、[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]の成形作業を3回行ったものです。

UCC3_1.12
腹側。
この状態で、1週目のUGA式造形クラブに持参しました。
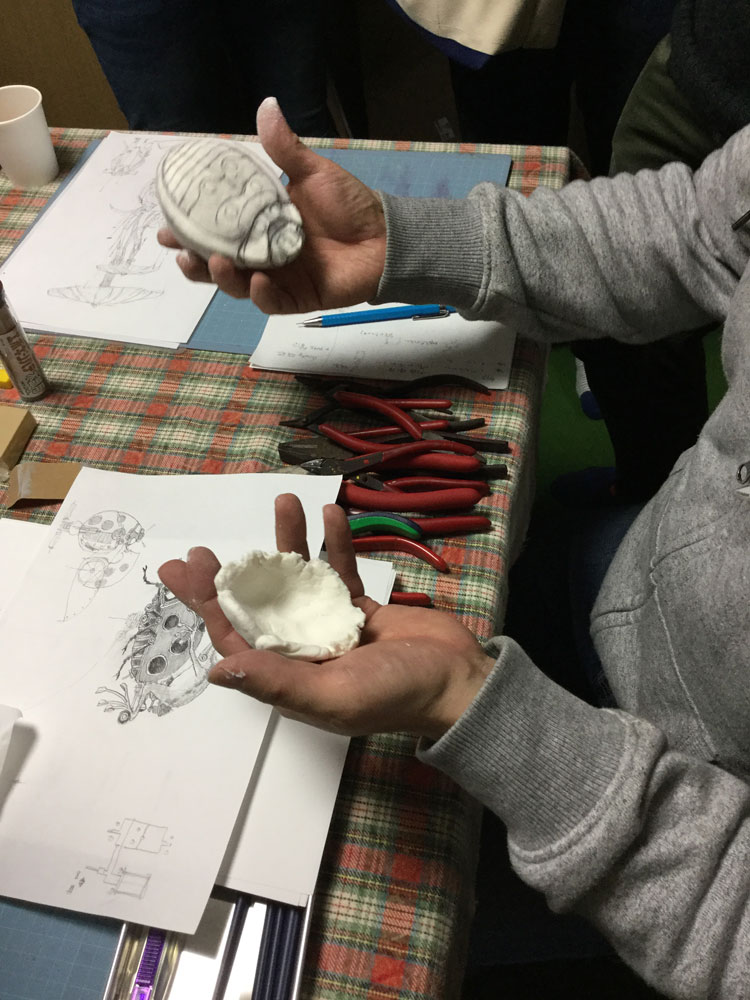
UCC3_1.13
3月12日の第1回目は、紙粘土加工を中心にレクチャーを行いました。

UCC3_1.14
テントウムシの大きさにあわせて、カエルを紙粘土で制作します。

UCC3_1.15
あわせて、サドルもつくります。

UCC3_1.16
乾燥後、基準線を目安に[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]作業を繰り返して成形していきます。

UCC3_1.17
カエルのボディがほぼ完成。
この画像で、[ヤスリ掛け→紙粘土つけ足し]の成形作業を3回行ったものです。
腕と脚は、テントウムシのハンドルとサドル、ステップの位置が確定しないと作業ができないので、
ここでいったんカエルは作業を止めておきます。

UCC3_1.18
サドルも同様におおよその形ができました。

UCC3_1.19
テントウムシは、外形全体の成形作業ができたので、上翅にある模様の位置出しを行います。
頂部のワッシャーを貼ったところは、ハンドルが取り付く予定。

UCC3_1.20
上翅は後の作業で肉厚を薄くするために内側から削る予定です。
そうなると、あまり強度がなく変形しやすいので、下端エッジ部分を金属線とエポキシパテで補強しておきます。
これは、この後行う分解作業の下準備も兼ねています。

UCC3_1.21
カッターで、頭胸部、上翅x2、腹側x2、ハンドル台座、サドル台座に分割します。
いっぺんに切り込みを入れるのではなく、少しずつカッターの刃を差し込み、徐々に切り込みを深くしていきます。
途中、切りすぎたり、力を入れて変形しても気にしません。大丈夫です。
後で、木工用ボンドで接着したり、紙粘土で補修したりして元に戻せるからです。これが紙粘土の長所のひとつです。

UCC3_1.22
画像は、上記のパーツを内側の状態がわかるように並べ直したもの。
これから、内部の加工とあわせてこれらのパーツを摺り合わせていきます。

UCC3_1.23
まずは、内部腹側に納める電池BOX(単5×2本用)の加工からはじめます。



